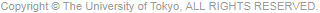教養学部報
第654号 ![]()
脳から見る多言語の自然習得
梅島奎立・酒井邦嘉
学生を含め日本人の多くは、英語などを「外国語」として長年勉強してきたのに「ほとんど話せない」という問題を抱えている。まして多言語を話すとなると特殊な能力だと思われがちだが、ヨーロッパやアフリカ・アジアの多民族地域では多言語環境が日常的であり、新たな言語の習得でもそれほど大きな苦労はないようだ。世界では半数から三分の二の人々が少なくとも二言語を日常的に使用しており、多言語環境の方が「自然な状態」であると言えよう。
思春期あたりから新たな言語の習得が難しくなるという「臨界期仮説」が一般に知られるようになって久しい。一方でそれは第二言語の積極的な使用をしなかったり、単語の記憶や読み書きの勉強に頼ったりする環境が原因との指摘もあり(酒井邦嘉著『勉強しないで身につく英語』PHP出版、二〇二二)、臨界期の科学的証拠は乏しい。そもそも言語能力、特にその核心となる文を生成する能力には、新たに習得すべきことなどないのかもしれない。
ノーム・チョムスキーが唱えた「生成文法理論」は、個人が持つ生成力に着目することで、言語間の差異が極めて小さいことを明らかにしてきた。あらゆる自然言語に普遍的な制約や生得的知識があるなら、個人における言語習得は、いわゆるスキルの学習とは全く異なる過程なのではないか。
一八〜一九世紀の言語学者フンボルトは、「言語を本当の意味で教えるということは出来ないことであり、出来ることは、言語がそれ独自の方法で心の内で自発的に発展できるような条件を与えることだけである。〔中略〕各個人にとって学習とは大部分が再生・再創造の問題、つまり心の内にある生得的なものを引き出すという問題である」(チョムスキー著、福井・辻子訳『統辞理論の諸相』岩波文庫、二〇一七、の中で引用)と結論づけた。
マサチューセッツ工科大学のスザンヌ・フリンと我々の共同研究では、第三・第四言語としてカザフ語(カザフスタンを中心に用いられ、テュルク諸語に属する)を新たに習得する過程で、脳活動がどのように変化するかをfMRI(機能的磁気共鳴画像法)で調べた。これまで言語の脳科学では、第一言語と第二言語の文法処理において共通して活動する脳領域(「文法中枢」)を同定してきたが、さらに第三・第四言語でも第一・第二言語と共通する神経基盤を持つかどうかはわからなかった。もしこのことが明らかになれば、その人にとって何番目の言語であるかにかかわらず全く同じ脳の機構がはたらいていることになって、言語の普遍性を立証することになろう。
実験は一四~二六歳の日本語母語話者、三一人を対象に行った。全員が英語を第二言語として習得しており、約半数はスペイン語など第三言語のリスニングテストで初級レベル以上のスコアを示した。カザフ語母語話者の音声刺激を用いた文法習得課題において、その文法規則は一切教えることなく、文の文法性と、文における主語・動詞の対応について、正誤の例を提示するのみにとどめた。その上で参加者の約半数が文法性や主語・動詞の対応を正しく判断できるようになるまで脳活動を記録した。
その結果、正答率が高かった群では、低かった群と比べて左下前頭回(図のL.IFG)と両側の側頭葉で有意に高い活動の上昇が見られた。また正答率が高かった群について、実験での最終段階と初期段階の比較、および正答率が高かった文構造と低かった文構造の比較においても、左下前頭回のみに有意な活動が限局した。このように「誰が」「何時」「何を」習得したかを示すそれぞれ三つの比較において、一貫して左下前頭回が賦活したのである。以上の結果から、「文法中枢」として知られるこの脳領域が、第一・第二言語に限らず第三・第四言語の文法習得でも重要な役割を果たすことが明らかとなった。
自然な言語入力である音声に触れるだけで、子どもから大人までも新たな言語の文法を柔軟に習得できるという本研究の成果は、言語の「自然習得」という考え方を支持する。これは、意識的な単語の記憶や文法の学習に頼るような語学教育に再考を促すものだ。

図 新たな言語で文の習得に必要な「文法中枢」の活動
言語をコミュニケーションと同一視する誤解があり、他者と共通した言葉や知識を習得することに重きが置かれがちだ。しかしそれは単なる「外言」に過ぎず、脳内の「内言」はそれと独立して構造(「統辞構造」と呼ばれる)に基づいて文を生成する能力―つまり個人のうちで再生・再創造する力―を前提としている。他者に伝わるかではなく自分にとって自然であるかを基準に言語を捉えるならば、個別の言語の間に本質的な差はなく、しかも言語の習得に制限などないことは明らかであろう。身近な言葉を多言語の視点から見つめ直すと、言語とは何か、知識の獲得とはどういうことか、という最大の謎が解けてくる。
(相関基礎科学/物理)
無断での転載、転用、複写を禁じます。