教養学部報
第581号 ![]()
<本の棚> 終わらない夢、 起きてもまた見てしまう夢
渡邊日日
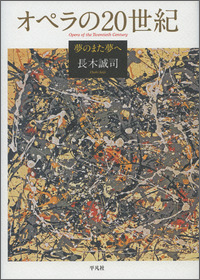
長木誠司 著
『オペラの20世紀:夢のまた夢へ』
(平凡社、2015年10月刊)著者について紹介文を今さら書く必要はない。評者の専門は、西洋古典音楽が評者にとって自己の存在の重要な一部になっているとはいえ、音楽学ではない。的確に評することなぞできやしない。本書は二段組みで800頁を越える大著である。しかるに、許されている書評の分量は400字詰め原稿用紙四枚ちょっと─ここでは好きに振る舞え、ということなのだろう。御意。
本書を通読して気づかされるのは、第一に、その立体的構成、別に言えば著者の多面的構想力である。本書で一定以上の紙幅が割かれ、そのオペラ作品が子細に論じられた20世紀の作曲家は、(読みながら数えていったところ)約60名(!)に上り、19世紀イタリア・オペラの「遺産」、ポストおよび反ヴァーグナー派の流れから始まり、ミニマリズムを通してのオペラの「逆襲」までカバーされている。しかし本書は、作曲家解説や作品解説のみから成り立っているのではない。考えてみれば、オペラというのは大がかりな装置であり、理念であり、様々なアクターたち(作曲家以外に演奏家、舞台芸術家、巨大な演奏会場、さらには仕掛け人なども必要だろう)による実現態である。従って、単なる挿話的エピソードとしてではない形で、例えば映画との関係や、文化的空間としての歌劇場、舞台での照明の歴史などについても、しかるべき記述と考察がなされることになる。以上の点で本書は、オペラというプリズムを通して見えてくる、20世紀の光(もちろん闇も)の全てを捉えようとする試みだと評することができよう。なお、同じ出版社の類書に、大崎滋生『二〇世紀のシンフォニー』(平凡社、2013)があるが、気短な方は章立てだけでも比較されたい。評者がここで言わんとする処は一目瞭然のはずである。
第二点。このような大著を計画するにあたって著者は、近代(ここで評者は、自己を批判し乗り越える運動としてそれを広く理解したが、著者曰く「オペラの脱貴族社会化・脱市民社会化、つまるところ近代化・現代化の努力が、意識的になされているか否か」125頁))がない日本・日本語文献のなかで、情報量が少ない作品・作曲家を出来るだけ取り上げようとしたという。しかし既に評したように、本書の特徴は充実した解説だけにあるのではないし、評者の何よりの読後感もそこから出てくるのではない。偶然の一致なのだろうが、本書も(正確には最後から六人目)、アレックス・ロス『二〇世紀を語る音楽』(柿沼敏江訳、二巻本、みすず書房、2010)も、大著の最後を、ジョン・アダムズの『中国のニクソン』で終えている。また、他の作曲家と比較して、長い頁が割かれているのがルイジ・ノーノとルチアーノ・ベリオというのも意味深だろう。二〇世紀におけるオペラと政治/物語という膨大なテーマの磁場はこうも強力なのだが、本書の最大の魅力は、そうした磁場の圏域に縛られることなく、何度も「死」の宣告を内外から受けつつも、自己蘇生していくオペラの生命力が描き出されている点である。その意味で本書の白眉は、第五部「オペラはどこへ?」と言ってよい。
最後に一つ、評者なりの悩みを。作曲家であり評論家でもあった諸井誠は『交響曲名曲名盤一〇〇』(音楽之友社、1979)の中で、「交響曲は、生と愛を謳歌する[メシアンの]《トゥーランガリーラ》と、死につかれた[ショスタコーヴィチの]《死者の歌》の間に引かれたデッドラインの上で、その命脈を絶った」(213頁)と、喝破した。交響曲を書き続けている作曲家は数多くいるなかで、である。となると、同じことが構造的にオペラに何故言えないのだろうか、オペラには著者のいう「過剰さ」が備わっていて交響曲にはないからなのか(確かにないかも)、そもそもオペラとは一つのジャンルを指す用語なのだろうか……悶悶。再読しろ、ということか。御意。
あれは確か高校一年だった。友人がアルバン・ベルクの「ヴォツェック」のレコードを貸してくれた。初めて聴くその音楽と筋の〈底なし感〉に私は震え上がった。あの時のような新鮮な驚きを再びもたらしてくれるオペラがまだ他にも、20世紀にはある。本書を片手にいざ、夢見ながら探索の旅に!
(超域文化科学専攻/ロシア語)
無断での転載、転用、複写を禁じます。

