教養学部報
第638号 ![]()
<本の棚> Riho Isaka 『Language, Identity, and Power in Modern India: Gujarat, c. 1850-1960』
大石和欣
イギリスから独立後のインドにおいて、文化や慣習を違えながら国内に広がる多数の言語と民族を、州としてどう再編成していくかは最大の難問の一つであった。とりわけグジャラーティー語やマラーティー語が関係するインド西部は複雑な背景を抱えていた。
国民会議派は、ボンベイ(現ムンバイ)市を中心とするボンベイ州を、一時はグジャラーティー語圏から成るグジャラート州、ボンベイ市、マラーティー語圏から成るマハーラーシュトラ州に三分するとしていたが、一九五六年八月に方針転換を表明し、ボンベイ州を二言語州として存続させた。
これに対し、その直後からグジャラーティー語話者の抗議と反発が激化する。同年八月八日、グジャラート地方の主要都市アフマダーバードで、学生ユニオンが国民会議派の建物前で抗議デモを行ったところ、警察が突如発砲して数名の死者が出た。学生犠牲者は「殉教者」として聖別され、グジャラーティー語を軸とした州の設立を強力に推進する抗議運動の原動力になっていく。最終的には一九六〇年にボンベイ州から、ボンベイ市を組み入れたマハーラーシュトラ州と、グジャラート州との二州が生まれることになる。
井坂理穂氏の本書は、社会と民族、宗教が錯綜するグジャラート地方での言語をめぐる議論が、イギリスによる干渉と植民地支配の下で、グジャラート州設立要求へとつながっていく数奇な命運を、精緻かつ多元的に辿った骨太のインド史研究である。
十二世紀頃に成立したと考えられるグジャラーティー語は、商業伝統の強いインド西部で用いられ、影響力はボンベイ市でも大きかったが、文学活動の言語としては格下に見られることもあった。グジャラート地方やボンベイ市ではヒンドゥー教徒だけではなく、ムスリム商人コミュニティのボーホラーらやゾロアスター教を奉じるパールシーも、異なる語彙や発音、表記を伴ったグジャラーティー語を併用し、他にも多様な「方言」が存在した。近代以前のグジャラーティー語は多様な形態をもつ流動的な言語であったのだ。
そんなグジャラーティー語が、州設立要求の基盤となるほどまでに、話者全体と結びついたアイデンティティの象徴となったのはなぜか。「標準語」の確立には教育が有効な手段だが、イギリスの実質的支配下において英語が果たす役割はあまりに大きかった。イギリス人支配階層とインドの民衆を媒介する「中間層」として台頭するインド人エリートは、初等・中等教育で土着言語を学んだとしても、高等教育では英語を修得せざるをえなかったのだ。土着言語としてのグジャラーティー語が高等教育において受け入れられる余地は十九世紀後半においても極めて限定的だった。
だが、そうしたなかでグジャラーティー語を標準語化しようとする動きが始まる。一八四八年にアフマダーバード市の補佐判事アレクサンダー・フォーブズによって設立された「グジャラート土着言語協会」では、グジャラートのエリートたちの主導により、会員数を増やしながら研究や定期刊行物を通してエリート階層のグジャラーティー語に対する意識改革が推進された。グジャラーティー語の学校教科書を編纂したり、富裕者からの寄付と庇護を通してグジャラーティー語文学を称揚することで、グジャラーティー語の標準化と地位向上に貢献した。
このようにグジャラーティー語が話者にとって「(想像の)共同体」意識を付与するものとなる過程では、上位カースト・エリートたちが大きな役割を担った。辞書を通した表記法の統一、古典語であるサンスクリットの語彙の摂取、ムスリムやパールシーが用いる「外国語」由来の語彙の排除などを通して、「純粋」で「元来の」グジャラーティー語を普及させるという観念が打ち出されていくことになる。グジャラートを代表する詩人となったナルマダーシャンカルは、グジャラーティー語がエリート階層にとって相応しい品位ある「正しく美しい言語」であることを主張するだけでなく、自身の詩を通して言語・文学改革を実践し、話者の意識を変革しようと試みた。皮肉なことだが、この一連の過程では支配者たるイギリスが施した英語教育や英文学教育の手法が模倣されることもあった。
当然ながらこの上位カースト・エリートによるグジャラーティー語の標準化、「サンスクリット化」はパールシーなどからの反発を喚起することもあった。そんな軋轢を乗り越え、多様な人々が共有できるグジャラーティー語の必要性や、これを「母語」として重んじることを説き、グジャラーティー語話者としてのアイデンティティを反植民地運動へとつなげたのがモーハンダース・ガーンディー(マハトマ・ガンジー)である。イギリスと南アフリカで名声を高めたガーンディーはグジャラーティー語話者であり、一九一五年にインドに戻るとイギリスからの独立運動を牽引した。彼にとって、英語という外から押しつけられた言語を排除し、インドの人びとそれぞれが自らの母語を通して自身と母語を母体とした文化を表現し、定義できることが重要であった。その一方でインドの人びとが相互に意思疎通を図る言語としてヒンディー語(ヒンドゥスターニー語)を提唱し、自らもこれを使用し、普及に努めた。
インド全体においても、グジャラーティー語話者にとっても「ナショナリズム」は一面的なものではない。グジャラーティー語話者の間では、自分たちの活動の一大中心地ともいうべきボンベイが他州に組み込まれてしまうことについて複雑な心情もあった。一方、グジャラートの「方言」話者、そして女性たちの間での言語認識は、上記のようなエリートたちのそれとは異なっていた。著者の目線は繊細にそうした「周縁」にも向けられながら、多様性に富んだグジャラートの言語をめぐる議論を通して、インドと帝国主義というマクロ史観を射程に収めている。読ませる理知的な文章で錯雑な歴史的過程を整理して語る本書は、インド史研究の亀鑑とも言え、今後の必読書になるだろう。
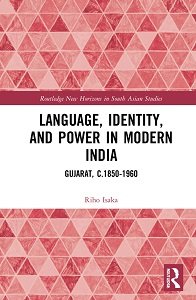
提供 Routledge
(言語情報科学/英語)
無断での転載、転用、複写を禁じます。

