教養学部報
第655号 ![]()
<本の棚> 伊達聖伸 著『もうひとつのライシテ――ケベックにおける間文化主義と宗教的なものの行方』
浜田華練
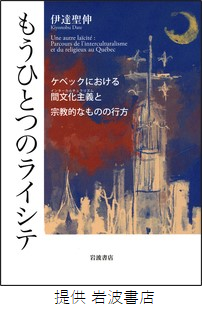 まず、タイトルが秀逸である。宗教から自律した公権力による個人の良心・信教の自由の保障を原則とする「ライシテ」という概念は、長年ライシテについて研究・発信してきた本書の著者の尽力もあり、近年日本でも人口に膾炙しつつある。その中で、「もうひとつの」ライシテとは一体何を意味するのか。
まず、タイトルが秀逸である。宗教から自律した公権力による個人の良心・信教の自由の保障を原則とする「ライシテ」という概念は、長年ライシテについて研究・発信してきた本書の著者の尽力もあり、近年日本でも人口に膾炙しつつある。その中で、「もうひとつの」ライシテとは一体何を意味するのか。
一般的な「ライシテ」は、共和政成立とともにフランスで発展してきたものを指すが、「もうひとつのライシテ」の舞台は、副題にもある通り、カナダのケベック州である。プロテスタントと英語話者が圧倒的なマジョリティを占める北米地域において、ケベックはカトリック教徒とフランス語話者が多数派をなす地域である。このケベック社会特有の文化・宗教・政治的土壌で育まれた、社会の統合と多様性の承認の両立をはかる「間文化主義」に即したライシテ、すなわち「間文化主義のライシテ」こそが「もうひとつのライシテ」に他ならない。
本書は、宗教を含めた多様な価値観を包摂する共生の枠組みとしての「間文化主義のライシテ」が結実する過程をケベックの歴史に沿って精緻に再構成した上で、ケベックの教育・司法の現場におけるライシテの具体的な展開を示しつつ、二〇一〇年代以降、公共空間からの宗教性の排除を指向する厳格なライシテがケベックでも主流になり、「間文化主義のライシテ」が後退していく点にも言及している。その上で、「間文化主義のライシテ」を、ケベックという限定された地域で一時的に生じた現象ではなく、「現在の世俗を基調とする文化多元的な社会のなかで、宗教をも含む多様な世界観を互いに理解し合うことで個人が豊かになり、そうした個々人の集まりとして構成される社会を、ライシテの名において構想する」(本書二一六頁)という、より普遍的なアプローチとして提示している。
著者がこうした野心的展望を示してくれたことに甘えて、ここでは、あえて本書の内容から(そして書評というジャンルの趣旨から)逸脱し、旧ソ連圏のキリスト教を研究する立場から、無理を承知で次のように問うてみたい。民主主義と政教分離が確立されており、人権が普遍的・絶対的価値と認められている前提条件の上に発展してきた「間文化主義のライシテ」という概念は、民主主義・政教分離が(西欧や北米ほどには)確立されておらず、人権も自明の価値とみなされていない社会に対して、どのようなインパクトを与えうるだろうか。
モスクワ総主教が、ウクライナ侵攻(ロシア国内でいう「特別軍事作戦」)の積極的支持を公然と表明している事実を挙げるまでもなく、現在のロシアでは、政権とマジョリティの宗教であるロシア正教が癒着している。モスクワ総主教庁が二〇〇〇年代に発表した、教会が構想するロシア社会の在り方を示す一連の文書は、「人権」を、近代西欧由来の「共同体の価値を毀損する個人主義」と「宗教に敵対的な世俗的ヒューマニズム」の産物とみなし、その価値を相対化する姿勢で一貫している。人権保障の原理としてライシテが提唱され発展してきたことを考えると、現状ロシアはそのスタートラインにすら立てていないのだが、希望がないわけではない。
本書の第一章で、ケベックにおけるライシテ概念の萌芽期に、フランス語圏のカトリック内部から生じた思想運動である「人格主義」が影響を与えたことが指摘されている。「人格」は、三位一体の神の個別性を指す位格に起源をもつ語である。これに対応するロシア語の「リーチノスチ」という概念は、神が個別の三者(父と子と聖霊)でありながら一体であるように、個別性を失うことなく共同体との一致のもとにある「個」の在り方を示す。この「個」の概念は、帝政末期のロシア宗教哲学とそれを継承した亡命ロシア人神学者たちによって豊かな知的発展を遂げた一方、全体主義・権威主義体制下では、むしろ個人の抑圧を正当化する論理として利用され、上述のロシア正教会の人権に関する理解もその延長線上にある。しかし、ケベックにおいて、ロシア的「個」の思想と薄く地続きにある「人格主義」が、個の尊重と社会の統合の両立を目指す「間文化主義」を生む土壌を育み、そしてそれが「ライシテ」と合流することで多元的社会における共生の原理として結実した事実は、ウクライナ侵攻以後のロシア思想史に、幽かな光を灯しうるのではないか。
本書は、フランス以外の地域に目を向けることで、ライシテをより普遍的な概念として提示し、日本のライシテ理解に一石を投じた。同時に、ケベック固有の現実に適応する形で「間文化主義的なライシテ」が結実していく過程を丹念に追った優れた地域研究でもある。それに加えて、「人格」という概念に起源をもつ「個」の在り方とそれを可能にする社会構想について、地域を超えた議論の場を拓いたことも、本書の重要な成果の一つに数えたい。
(地域文化研究/ロシア語)
無断での転載、転用、複写を禁じます。

