教養学部報
第656号 ![]()
<本の棚> 田原史起 著『中国農村の現在「14億分の10億」のリアル』
関谷雄一
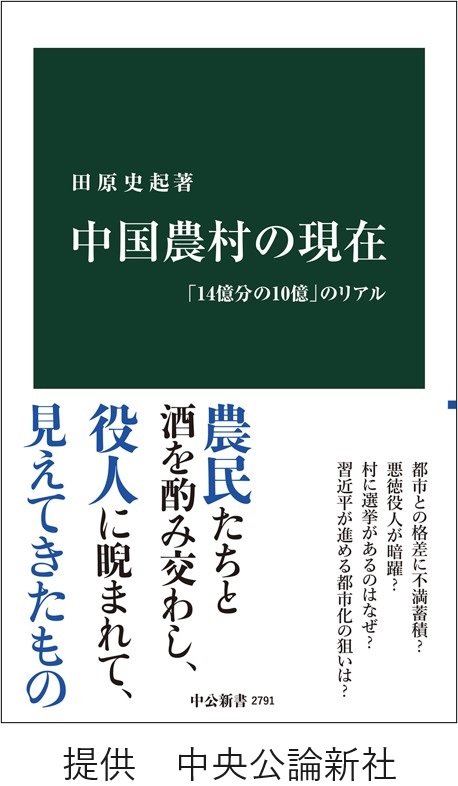 中国は近くて遠い国である。漢字や中華料理など日常生活の様々な場面で中国文化の断片に触れることはできるし、本学の学生や教職員の方々にも中国出身者は多く、個人的なふれあいから、感得できることも多い。しかし、正面から文化交流や外交、安全保障といったテーマで同国に接近しようとすると、ニュースなどで報じられている現実を見るにつけ、日中関係は両国の歴史にも起因する難しさがある。昨今ではプロによる現地調査すら難しい状況にある。まして、中国研究者でもない私のような人間にとり、中国は謎多き国だ。さらにその農村でどんな生活が営まれているかなど、想像もつかない。
中国は近くて遠い国である。漢字や中華料理など日常生活の様々な場面で中国文化の断片に触れることはできるし、本学の学生や教職員の方々にも中国出身者は多く、個人的なふれあいから、感得できることも多い。しかし、正面から文化交流や外交、安全保障といったテーマで同国に接近しようとすると、ニュースなどで報じられている現実を見るにつけ、日中関係は両国の歴史にも起因する難しさがある。昨今ではプロによる現地調査すら難しい状況にある。まして、中国研究者でもない私のような人間にとり、中国は謎多き国だ。さらにその農村でどんな生活が営まれているかなど、想像もつかない。
そのような国に赴き、辺境の村まで入り込んでは、人々と確かな絆をつくり、その人々の素顔をしっかりとらえて研究を続けているのが筆者である。本書は、これより少し前に東京大学出版会から出版された筆者による社会科学の研究書『草の根の中国─村落ガバナンスと資源循環』の舞台裏を描くように、その内容には豊富な調査データに基づく分析に加え、中国研究者としての筆者の行動や考えが、一般の読者にも分かりやすく書かれている。中国社会を対象とした調査や研究を志す方は是非、両者を手に取って読むと面白いと思う。
本書は筆者自身が立てた五つの問いを順番に考察していく筋書に沿って書かれている。⑴中国の農民とは、どのような歴史的経験をもち、どういう思考様式を有する人々なのか。⑵現在の農村の暮らしはどのようなものだろうか。⑶統治者である中国共産党中央と中央政府は、国内の農村をどう位置付けているのか。⑷私たち外国人による中国の農村調査はなぜ、しばしば「失敗」するのだろうか。⑸現在、中国政府が進めている「新型都市化政策」は、農村社会にとりどんな意味を持つのだろうか。
本書の記述を通して説明される、以上の問いに対する答えは次のようになる。⑴中国の農民は、歴史の早い段階から「家族主義者」となり、個人を中心とした自己責任意識と努力によって、社会的上昇を目指して生きようと考えている。⑵農村では「基層幹部」と呼ばれるフォーマル・リーダーが、共産党と農民とをつなぐ役割を担いつつ、人々の暮らしが維持されている。⑶権威主義的な共産党・中央政府の体制と、農民自身の家族主義が共鳴し合い、さらに、その状態を基層幹部が制御することで維持を図ろうとしている。⑷調査は、農村の人々に「身内」に近い人間だと感じさせる努力と、外国人に対し排他的な政治体制において「自由の隙間」が見出せるような好機がそろわない限り難しい。⑸中国政府がいう都市化とは大都市に農村の人口を集中させる政策などではない。都市と農村の双方を含む最もコンパクトな地域社会である県を単位に、県の中心都市、県城に農民工を集め、都市と農村の機能を共に維持させること、なのである。
上記の大筋に加えて本書から学ぶべきは、筆者による中国研究における「宴会」あるある話だ。飲酒をともなう宴会とどう向き合うべきか(コラム1)、宴会を利用して逆に体よくあしらわれてしまう話(コラム2)、小麦の主食でおなかを満たしてから飲む北方の酒席(コラム3)、肉類を中心とした副食と酒で長時間続けられる南方の酒席(コラム4)、農村におけるフォーマルな宴席は、芝居や演劇における「場面」の転換と考えると理解しやすいという話(コラム5)。どれも中国各地の農村を渡り歩いてきた筆者ならではの発見だ。
フィールドワーカーの端くれである私にとり、最も強く印象に残った部分は、筆者による「オレ流」中国農村調査の記述だ。数々の失敗から得られた筆者の調査の「好み」が記されている。それぞれ、現場を好む、単独を好む、平凡を好む、散歩を好む、出来事を好む、反復を好むという言葉に集約されるポイントである。これらのポイントは、中国だけではなく、恐らく世界のどこに行っても、大なり小なり当てはまるフィールドワークのエッセンスであり、ただ首肯するばかりである。
(超域文化科学/文化人類学)
無断での転載、転用、複写を禁じます。

