教養学部報
第656号 ![]()
<本の棚> 齋藤希史・田口一郎 著『漢文の読法 史記 游俠列伝』
矢田 勉
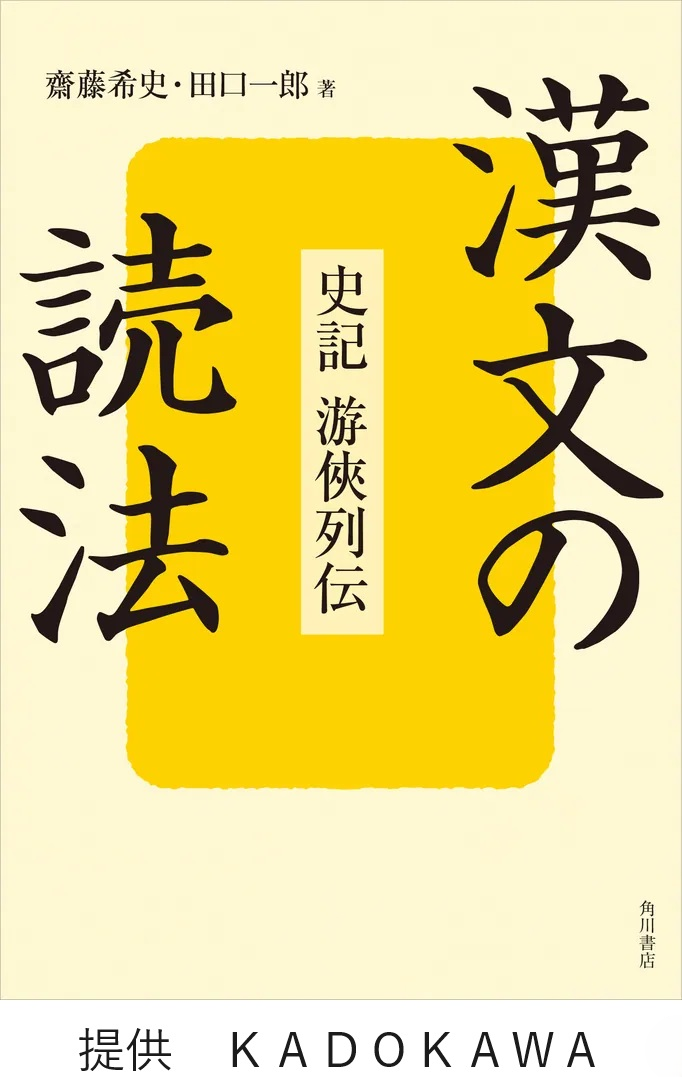 これから本書の紹介をしようとする私であるが、前期課程学生の時には、竹田晃先生の『論語』の授業でたいそう悪い点を頂いた体たらくである。『論語』を現代語訳する試験問題に対して、「孔子の言うには、『何事かを学んでそれを復習することは、なんと楽しいことじゃ。......』」という調子で、孔子の発言部分をみな「...じゃ。」と訳した結果、ぎりぎり落第お目こぼしの評価を頂戴したのだった。
これから本書の紹介をしようとする私であるが、前期課程学生の時には、竹田晃先生の『論語』の授業でたいそう悪い点を頂いた体たらくである。『論語』を現代語訳する試験問題に対して、「孔子の言うには、『何事かを学んでそれを復習することは、なんと楽しいことじゃ。......』」という調子で、孔子の発言部分をみな「...じゃ。」と訳した結果、ぎりぎり落第お目こぼしの評価を頂戴したのだった。
そんなことをしたのは、直接には下村湖人『論語物語』の影響であるが、さらに根源を言えば、漢文というものの本質を理解していなかったからである。高校の国語科で古文・漢文と並称されることもあって、漢文は古文と本質的に性格の異なる文字言語であることが当時の私には分かっていなかった。古文(和文)は本来、都の貴族たちという、狭くかつ均質なコミュニティの中でのみの通用を想定して創出された文字言語であって、彼らが日常使用する口頭言語との密着度が高かっただろうものである。それに対し漢文は、言語にも文化にも夥しい多様性を内包した広い中華で通用させるために作られた文字言語である。口頭言語にある様々な要素や違いを捨象して、人工的に作り出されたものである。
竹田先生は、ただ単に「...じゃ。」にかちんときた、というのではなかったのだと思う。私の、漢文の本質を知らない不勉強を見抜かれたのである。念のため、『論語物語』はあくまで「物語」であって、下村湖人に何ら責められるべきところがないのは勿論である。
そういうわけであるから、和文は、平安時代当時の貴族たちにとっては、取り立てて努力せず読めるものだったであろう。しかし、漢文は初めから口頭言語と隔たりのある文字言語であるから、全ての読み手に、それを解釈するための伎倆が求められる。現代の国語教育論で言われる「創造的な読み」などというレベルではなくて、読み手側が解釈を創造することではじめて言語記号としての機能そのものが全うされるのである。
であるからこそ、中国人であってもほとんどの場合、漢籍は注釈を付したものを使って読み継いできた。自分の解釈伎倆の不足を、読み巧者が付けてくれた注で補うのである。日本人読者の場合には、これに「訓読」という名の翻訳作業が加わるから、求められる創造性には、中国人読者よりも一層大きなものがある。
漢文の訓読文は、読者によって能動的に作られるものである。決して、原文に機械的な記号変換を施せば産出される、というようなものではない。しかし、日本のある時期以降の(ことによると早くも遣唐使廃止後の)漢文教育は、そこのところを学習者に明瞭に示してくれないきらいがあった。あたかも訓読文が初めからそうあるべきものとして存在しているかのような印象を与える教育法が多かったのである。江戸時代以降に普及する「素読」などはその最たるものである。それでも、素読を愚直に繰り返すことによって、いつか訓読文の裏に潜む解釈が透視できてくる、ということはあったのだろう。しかし、それは漢文学習が学業の中核にあった時代にはできたことでも、現代の我々に同じことをする余裕はない。結果として、出来合いの訓読文を一方通行的に与えられ、それが漢文嫌いを生むことになる。まず、訓読文をただ丸暗記するのに倦む人が出てくる。それを乗り越えてもう少し踏み込んだ学習者は、ありうる訓読文はただ一つではないということに気づくものの、許される訓法と許されない訓法の境目が今ひとつ理解できずに嫌になってしまう。
もうお分かりだと思うが、そうした落とし穴にはまらず、漢文の正しい理解に至る近道は、漢文を解釈し訓読文を作る過程を、自ら主体的にたどってみることである。本書は、現代日本の読み巧者が、『史記』という親しみやすいテキストを通じてその道筋を惜しげなく披露してくれた、これまでありそうで無かった指南書である。ここではその具体的な内容には触れることが出来なかった。それは、断片的な引用ではなくて本書の全部を、できる限り多くの人に体験してもらいたいからでもある。前近代の日本では、人文・社会科学、自然科学の別なく、ほぼ全ての学問の基盤に漢文があった。自分が学ぼうとする研究領域の淵源を尋ねれば、必ず漢文文献に行き当たる。本書は、日本で学び研究する限り、どんな人にも益ある本である。
(言語情報科学/国文・漢文学)
無断での転載、転用、複写を禁じます。

