教養学部報
第657号 ![]()
<本の棚> 田尻芳樹 著 『日常という謎を生きる ――ウルフ、小津、三島における生と死の感触』
郷原佳以
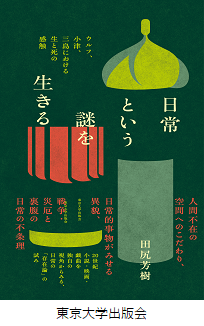 「日常」と聞いてどんなイメージを抱くだろうか。ネガティヴなイメージもポジティヴなイメージもあるだろう。朝起きて顔を洗い歯を磨き満員電車に揺られ、昨日と明日と変わらぬルーティーンをこなす、そのようなものだとすれば「日常」と退屈は同義で、対義語は冒険や驚異であろう。地球のレベルでは人間とは比べものにならぬほど日々昼と夜が繰り返されているのだが、人は古来、新しいことを追い求めてきた。しかし、大地震のような災害で日常生活がままならなくなると、日々の習慣のありがたみを実感し、旅行から帰ってきたときなども、いつもと同じであることに安心感を覚える。では、本書が「断想(序に代えて)」で喚起しているように、日常がすでに非日常であるような戦場や強制収容所はどうか。そこでは安らぐことができないにもかかわらず、逃げることもできない。本書は日常を焦点化する作品を分析しているが、読み進めてゆくと、日常ほど軽いがゆえに重く、凡庸ゆえにノイズを孕む謎はなく、ある種の文学にとって日常を超える主題はないという認識に辿り着く。
「日常」と聞いてどんなイメージを抱くだろうか。ネガティヴなイメージもポジティヴなイメージもあるだろう。朝起きて顔を洗い歯を磨き満員電車に揺られ、昨日と明日と変わらぬルーティーンをこなす、そのようなものだとすれば「日常」と退屈は同義で、対義語は冒険や驚異であろう。地球のレベルでは人間とは比べものにならぬほど日々昼と夜が繰り返されているのだが、人は古来、新しいことを追い求めてきた。しかし、大地震のような災害で日常生活がままならなくなると、日々の習慣のありがたみを実感し、旅行から帰ってきたときなども、いつもと同じであることに安心感を覚える。では、本書が「断想(序に代えて)」で喚起しているように、日常がすでに非日常であるような戦場や強制収容所はどうか。そこでは安らぐことができないにもかかわらず、逃げることもできない。本書は日常を焦点化する作品を分析しているが、読み進めてゆくと、日常ほど軽いがゆえに重く、凡庸ゆえにノイズを孕む謎はなく、ある種の文学にとって日常を超える主題はないという認識に辿り着く。
もちろん、文学が元来そうであったわけではない。前述の通り、人は昔から新しいことに心を躍らせる存在であったから、主人公が日常から抜け出して冒険の旅に出て驚異に出会う物語が多数生み出されてきた。しかしある時期から、何ということもない日常の瞬間に驚異を見出し、あるいは何も起こらない日常の起こらなさそのものを描こうとする作家が現れてきた。著者が専門とする20世紀モダニズム文学、とりわけヴァージニア・ウルフやサミュエル・ベケットがそうである。本書はこの二作家に加え、三島由紀夫、イアン・マキューアンの小説、小津安二郎の映画の分析を通して、日常に向き直る作家の眼差しを浮かび上がらせる。本書がとりわけ気づかせてくれるのは、日常は物でできているということである。これらの作家たちは卑近な日常的事物を前景化するのだ。
先に、日常は人に安心感を与えることを確認したが、ウルフ作品をめぐる第一章で著者は、『ダロウェイ夫人』でクラリッサが鏡や化粧台といった周りの事物を初めて見るかのように感じたり、いつも通りの家の様子に安心感を覚えたりするのは、彼女が死の恐怖に囚われているからだと指摘する。自分がいま生きていることが当たり前でないと感じられるとき、色褪せた事物が鮮やかに見えるのだ。ウルフ作品に死への恐怖を読み込む方針は、著者の読解に一貫している。ウルフの人物たちは自己の死を乗り越えるかのように周りの人や植物に一体化し、ウルフが人間不在の空間で事物を描くのは、死すべき人間との対照においてである。興味深いのは、かくしてウルフにおいては死への恐怖という人間的な心情が同時に非人間的な世界把握に繋がっていることである。というのも著者によれば、人間不在の空間における事物の描写は、ウルフの人物たちがときおり巡らせる〈自分が死んだ後の世界の想像〉の延長線上にあり、これは非人間的な映画的知覚に他ならないからだ。ここから、無人の空間で日常的な事物が前景化される小津映画をめぐる第二章へと続く第一部の構成はスリリングだ。ウルフと小津が共有しているのは、物語映画に先立つ初期映画的な感性なのだ。
第二部で分析される三島においては、平凡で呑気な日常は基本的に呪詛の対象である。しかし、唾棄すべき日常は待望される非日常―死と世界崩壊―と表裏の関係にあり、ふとした瞬間に「転位」して鮮烈な姿を見せる。そこでの事物はサルトルの『嘔吐』でロカンタンが直面するマロニエの根に相当し、そうしたヴィジョンが死を意識した切迫感のなかでもたらされる点にはカミュの『シーシュポスの神話』的な不条理性があるという指摘はいずれも説得的だ。
三島における破局と日常の表裏一体性が鮮やかに示された後、第三部のベケット論では、冷戦以後の人々が抱えるトラウマと核戦争の脅威を背景に、破局後に続くうんざりする日常の時間表象が分析される。マキューアンの『土曜日』を論ずる最終章では、九・一一以後の集団的不安を背景に、破局的出来事から反射的に日常に回帰しようとする「慣性」的心理が浮き彫りにされ、最後に第一章のウルフ作品分析と接続される。
私たちは大抵、日常に埋没している。埋没されるものこそ日常であり、埋没できることが日常なのだから当然である。しかし、何らかの要因で日常からの疎隔が起こると、日常的事物は有機的連関を解かれて物として現れる。これ自体は「異化」や「デペイズマン」といった用語で20世紀の芸術潮流が追究してきた事態だ。無意味さの露呈という点では「不条理」もこれに近い。本書はしかし、非人間的な状況に残存する日常ほど不気味かつ驚異的なものはなく、作家たちは各々の時代的感性でそれを描いてきたということを具体的に示す。戦争が終わらない21世紀の現代にも完全に通じる感覚だ。
(言語情報科学/フランス語・イタリア語)
無断での転載、転用、複写を禁じます。

