教養学部報
第657号 ![]()
<時に沿って> 動き、動かず、「動くこと」を考える
住吉康大
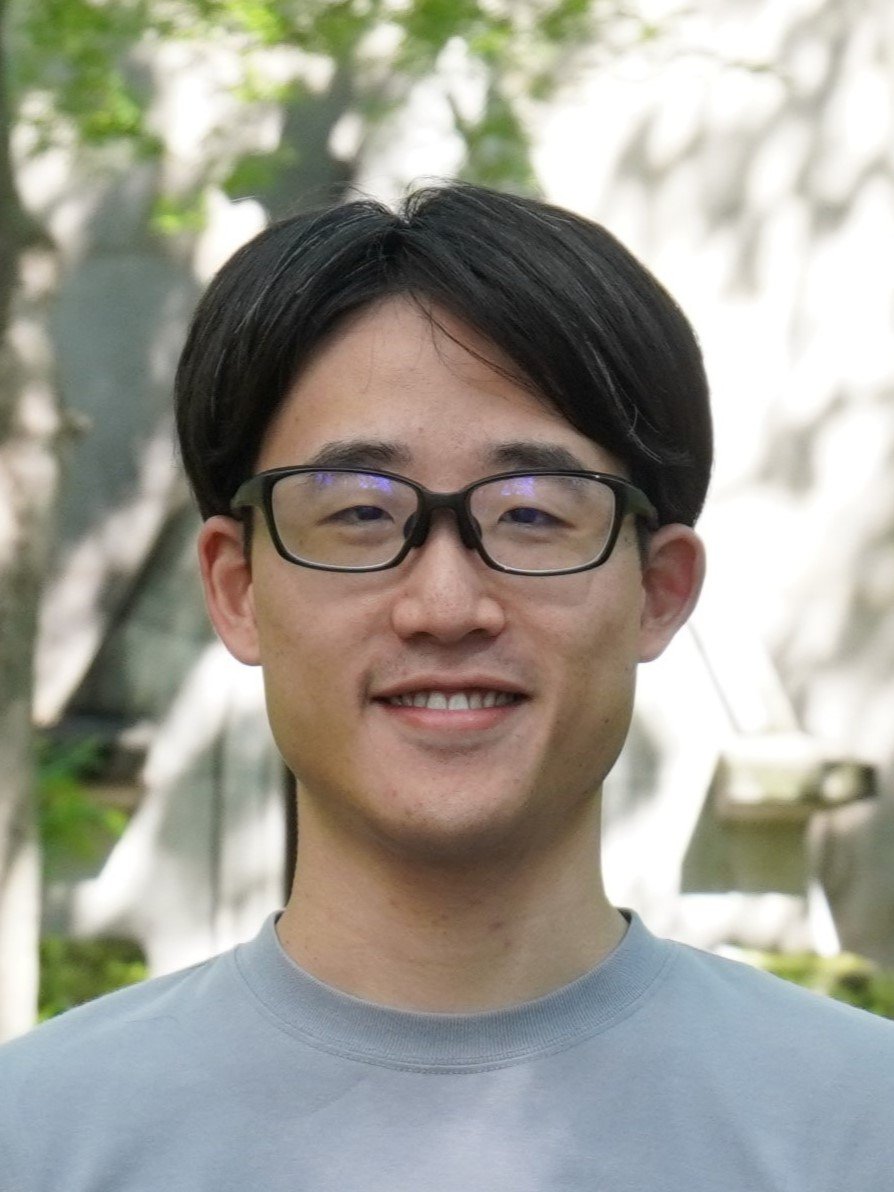 二〇二四年七月一日に、総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系の助教に着任しました、住吉康大と申します。専門は人文地理学で、「アドレスホッパー」や「多拠点生活」と呼ばれるような、あちこちを行き来しながら暮らす生活と、人々について研究しています。
このテーマに関心をもったきっかけは、故郷・鹿児島を旅立ち、進学してきた時の衝撃でした。当時は「地方消滅」「地方創生」が声高に叫ばれており、人に溢れる街を目の前に「もっと皆が色んな所へ移住すればよいのに」と思っていました。しかし、東京に生まれ育った同級生たちはこの地に愛着を持っていること、仕事や娯楽など様々な面で、ここにしかないものがたくさんあることを体感するにつれ、自らの浅はかな考えを恥じました。その中で、移住の難点を補ってくれる方法として注目されていた「あちこちを行き来しながら暮らすこと」が気になり、その理想と現実を知りたいと思うようになりました。
二〇二四年七月一日に、総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系の助教に着任しました、住吉康大と申します。専門は人文地理学で、「アドレスホッパー」や「多拠点生活」と呼ばれるような、あちこちを行き来しながら暮らす生活と、人々について研究しています。
このテーマに関心をもったきっかけは、故郷・鹿児島を旅立ち、進学してきた時の衝撃でした。当時は「地方消滅」「地方創生」が声高に叫ばれており、人に溢れる街を目の前に「もっと皆が色んな所へ移住すればよいのに」と思っていました。しかし、東京に生まれ育った同級生たちはこの地に愛着を持っていること、仕事や娯楽など様々な面で、ここにしかないものがたくさんあることを体感するにつれ、自らの浅はかな考えを恥じました。その中で、移住の難点を補ってくれる方法として注目されていた「あちこちを行き来しながら暮らすこと」が気になり、その理想と現実を知りたいと思うようになりました。
とはいえ、実際の調査は容易ではなく、常々手探りで進めてきました。二〇二〇年からはコロナ禍に見舞われ、移動の制限と先行きの見えない不安に押しつぶされそうになりました。二〇二二年からは、実際に移動しながら暮らす方々に日記を付けていただき、やり取りする調査を始めました。日本中を飛び回る皆さんからの日記帳を待ちつつ、自宅からオンラインでインタビューをし、時々キャンパスや郵便局に出かけるばかり、という奇妙な動と静のコントラストが際立つ日々。振り返れば、人の、モノの、情報の、色々な「動き」について考えるにはこの上なく貴重で、特別な時間を過ごせたと思っています。
出会った方とお話していると、「住吉さんも旅が好きなんですか?」「あちこち行くと新しい発見があっていいですよ!」と言われる機会がとても多いのですが、何とも裏腹なことに、ずっと駒場キャンパスに通い続けてかれこれ十年目を迎えます。今回は縁あって、学生から教員へという大きな「動き」を経験することになり、居室の引っ越しもしましたが、それとて同じ建物の中。距離にすればわずか数十メートルに過ぎません。しかし、本棚や机を並び替えるだけで、全く別の場所に来たようで、不思議と気持ちが新たになるものです。改めて、人間にとっての移動、そして場所との関係というのは興味深いものだと感じています。
ふと、乗り慣れた井の頭線に揺られていると、移動で人生を豊かにしよう、と謳う本の広告が目に入りました。どうやらもうしばらく、歩き慣れた駒場から、「動くこと」を考えることになりそうです。いつかここを旅立つその日に備えて、なお一層精進しなければならないと、気持ちを引き締める日々です。これからどうぞよろしくお願いいたします。
(広域システム科学/人文地理学)
無断での転載、転用、複写を禁じます。

