教養学部報
第660号 ![]()
<本の棚> 阪本拓人、キハラハント愛 編 『人間の安全保障 東大駒場15講』
永田淳嗣
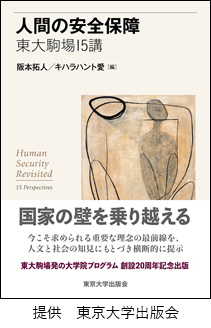 本書のテーマである「人間の安全保障(human security)」とは、編者の一人である阪本が序論の冒頭で述べているように、一九九〇年代半ば以降、国際社会で広く議論されるようになった概念である。冷戦後という文脈を背景に、新たな国際秩序を構想していく上で、「国家の安全保障」あるいは「国家による安全保障」を重視する従来からの立場に対し、視座を転換し、人間を安全保障の中心に据え、その実現を複層的なしくみによって実現することの重要性を訴えるものであった。しかしそれから三十年、阪本の論述・分析によれば、国際社会において、人間の安全保障概念が広く受容され、その実践が図られているとはいいがたい状況にあるという。この概念が国家の主権との緊張関係をはらむことから、当初からそれを忌避する立場があることや、人間の安全保障に包摂される事象が幅広く、個々の課題に対しては議論や実践が蓄積され、この概念の付加価値が不明確であるといった批判がその根底にあるという。それでもなお、「人間の安全保障を追求し探求し続ける意義」は何であるのか、阪本が強調しているように、この概念が登場して三十年も経つ以上、そのことが問われてしかるべきであるし、その手がかりを与えることは、このタイミングで出版された本書に課せられた重要な課題といえるだろう。
本書のテーマである「人間の安全保障(human security)」とは、編者の一人である阪本が序論の冒頭で述べているように、一九九〇年代半ば以降、国際社会で広く議論されるようになった概念である。冷戦後という文脈を背景に、新たな国際秩序を構想していく上で、「国家の安全保障」あるいは「国家による安全保障」を重視する従来からの立場に対し、視座を転換し、人間を安全保障の中心に据え、その実現を複層的なしくみによって実現することの重要性を訴えるものであった。しかしそれから三十年、阪本の論述・分析によれば、国際社会において、人間の安全保障概念が広く受容され、その実践が図られているとはいいがたい状況にあるという。この概念が国家の主権との緊張関係をはらむことから、当初からそれを忌避する立場があることや、人間の安全保障に包摂される事象が幅広く、個々の課題に対しては議論や実践が蓄積され、この概念の付加価値が不明確であるといった批判がその根底にあるという。それでもなお、「人間の安全保障を追求し探求し続ける意義」は何であるのか、阪本が強調しているように、この概念が登場して三十年も経つ以上、そのことが問われてしかるべきであるし、その手がかりを与えることは、このタイミングで出版された本書に課せられた重要な課題といえるだろう。
東京大学駒場キャンパスでは、二〇〇四年に大学院総合文化研究科において「人間の安全保障」プログラム(HSP)が立ち上げられ、人間の安全保障概念の学術的な深化を図ると同時に、実践を志向する学生を幅広く受け入れ、学術と実践の共創を図る試みが継続されてきた。本書は、HSPの運営に参加した、人文・社会科学の様々な分野をバックグラウンドに持つ教員・研究者の論考をまとめたHSPのテキストの第二弾、十六年前に出版された第一弾のテキスト(高橋・山影『人間の安全保障』二〇〇八年)の後継版にあたるものである。ただしテキストとはいっても、目次を一瞥すればわかるように、人間の安全保障の歴史、背景、概念、方法、実践といったことが体系的に論じられているわけではない。本書の共編者であるキハラハントが結論で指摘しているように、確かに本書を構成する十五の論考全体を通じてみれば、具体的な事象を通じて、人間の安全保障にとっての本質的な要素や実践に必要な考察が浮かび上がってくる。とはいえ、各論考が取り上げる事象は、人間の安全保障という言葉から直ちに想起されるような難民、紛争、被災者といった対象にとどまるものではないし、参照する時間・空間の幅は極めて広く、そのアプローチ、論じ方もそれぞれの専門性を背景に多彩である。
阪本が序論で述べているように、本書に収められた十五の論考に共有されているのは、「より人間的な地球社会への志向性」という人間の安全保障の根源的な部分ということになるだろう。そのことを了解した上で、私なりに感じ取った、本書の論考群にみられる特徴に関して、二点ほど述べておきたい。一つ目は、複数の論考が、人間の安全保障で守られるべき人間性(人間らしさ)に対して踏み込んだ洞察を行っている点である。人間の安全保障を構成するとされる、恐怖からの自由、欠乏からの自由、尊厳を持って生きる自由の中でも、尊厳に関しては、それがどのように形成され、どのように人間性と関わっているのかを客観的に記述したり理解することは必ずしも容易ではない。またある個人の尊厳を守ることが、当人や他者の人間性を損ねる、あるいは否定することがあり得る点にも注意が向けられている。二つ目は、多くの論考が、繊細な網の目の中で人間性が支えられている状況への洞察を行っている点である。その洞察の範囲は、公的な法・制度からそれを動かす主体、様々なレベルの社会関係、さらには人間と人間との間を媒介する要素にまで及んでいる。
「人間の安全保障を追求し探求し続ける意義」を本書に読み取るとすれば、様々な分野の多くの研究者が、人間の安全保障というテーマに向き合う機会を持つことで、より人間的な学術の体系を模索する契機を与えられることになり、その実践の積み重ねが、学術と人間社会との新たな関係の構築に寄与していく可能性ということになるのではないかと考える。
(広域システム科学/人文地理学)
無断での転載、転用、複写を禁じます。

