教養学部報
第661号 ![]()
<時に沿って> 自国史研究者がなしうること
前田亮介
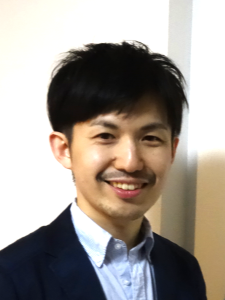 駒場の国際関係論の黎明期を支えた西洋史家・江口朴郎(一九一一~一九八九)は、一九五四年十二月、法学部に出講した「外交史」の講義で次のように語っています。
駒場の国際関係論の黎明期を支えた西洋史家・江口朴郎(一九一一~一九八九)は、一九五四年十二月、法学部に出講した「外交史」の講義で次のように語っています。
ともかく是迄の歴史はヨーロッパの―それも大国中心の歴史であつた。ヨーロッパでさえも、バルカンとかスペイン等は近代化の点に於いては甚だ封建的な残滓も多いし後進的でもある。近代日本の発展などは、ヨーロッパ強国の近代的発展の基準からみて例外のように云われるが、むしろかゝる変則的な地域を沢山作つて来たのが近代世界であり、そのことが現在大きな反省を促されている一面を看過してはならない。国家理性の問題は、その前提の上で考慮さるべきものであろう。そのようにしてはじめていわゆるpower politicsの問題を考えることができる。
はじめてこれを読んだとき日本政治外交史を生業とする私の心を捉えたのは、「近代日本の発展」の「例外」論(これは例外的発展論より、当時全盛だった講座派流の近代主義による「遅れ」と「歪み」論でしょうが)を戒める、ニュアンスに富む「近代世界」像でした。国際政治(史)は「大国」中心で描きえない不均衡でまだら状のものであり、アジア・アフリカはもちろん、ヨーロッパ内にさえ存在した「変則的な地域」こそ普遍的だという、今日の世界の混沌を予見するような含意をそこに読みとることもできます。
なにより、日本政治外交史が変則性とそれゆえの普遍性を備えているとすれば、それは何なのか。戦前の日本が主たる専門である私は、十九世紀の急速な近代化、戦間期の相応の民主化、そして帝国の膨張と崩壊、という日本列島の劇的な歴史を、どのように他地域との比較に開かれた言葉で位置づけうるのか、常々悩んでいました。自国史研究者の抱える問題は、自国史の重要性が学問的にも社会的にも自明であることです。外国(史)研究者が引き受けるだろう「なぜわざわざそれを?」を説明する緊張感は共有しませんし、さらに学問的分業化も進んでおり、その国の政治外交における現在進行形の事態と格闘する緊張感を持つことも求められません。
そうした自国史研究者からすると、江口の「外交史」が、一方で東側の大国を例に「国家理性」論にも依然優れた説明能力があることを示しつつ、他方で既存の大国中心の歴史叙述に「反省」を迫ったことは、日本研究を世界史に接続する一方途としてしごく魅力的に感じられました。それは、図式的なマルクス主義史家という、江口に対する私自身のステレオタイプが崩れた瞬間でもありました。
もちろん当時、この数年後に駒場とご縁があるとは知る由もありません。また前任校の北海道大学法学部で同僚と十年半もの豊かな時間を共有しなければ、こうした自明性への葛藤もなかったでしょう。考えてみると、学生時代は「歴史学」の、北大では「政治学」の、そして駒場では「国際関係史」の一分野として、私の自国史研究をそれぞれ鍛える機会をいただけたのは、幸運だったかもしれません。学際的な駒場の環境で私に今後生じるだろう化学反応を楽しみつつ、普遍的な知見に貢献しうる自国史研究者として研鑽を積みたいと思います。
(国際社会科学/国際関係)
無断での転載、転用、複写を禁じます。

