教養学部報
第661号 ![]()
<時に沿って> 音声と私
平山真奈美
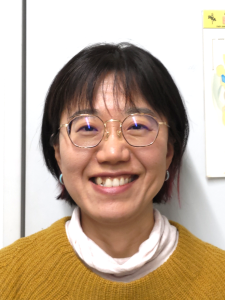 二〇二四年十月一日付で着任いたしました。専門は、言語学、特に音声に関わる部門で、音声学、音韻論と呼ばれます。とは言っても、音声は言語の各方面に関わっているので、語や文全体の構造を考えたりすることも多いです。
二〇二四年十月一日付で着任いたしました。専門は、言語学、特に音声に関わる部門で、音声学、音韻論と呼ばれます。とは言っても、音声は言語の各方面に関わっているので、語や文全体の構造を考えたりすることも多いです。
「時に沿って」音声への興味がいつから自分にはあったのかしら、と考えますと、はっきり思い出せるのは、中学校に入って初めて英語を教わった時に、thの発音やrの発音など、日本語にない音に興味を覚えたころのように思います。その後、英語自体好きでしたが、小説にのめりことむとかというよりは、声に出して英文を読んだりすることが好きでした。
今私が音声学・音韻論に携わっていることにつながる次の大きなマイルストーンは、大学一年生の時に英語音声学の授業を履修して、音声が学問できるということを知ったことでしょう。なにやら、音声を分解して記述したりしているではありませんか。衝撃的に面白かったです。とはいえ、学部時代は言語学以外のことにも興味があったので、言語学の学生としては勉学が足りなかったわけなのですが、卒論ではカナダ英語のことを調べて、大学院へ進み、音声学や言語学一般のトレーニングを受けながらカナダ英語の母音についての修士論文を執筆しました。そうこうしているうちに、奨学金をいただける目処がたったため、留学ができることとなり、トロント大学へ行きました。トロント大学の言語学科はファミリーのような雰囲気で、学科内でも、また、大学の寮でも質の良い異文化を経験しました。トロントでは、お互いの多様性を尊重する環境で生活を送ることができ、理論をきちんと考えるなど、アカデミックにも素晴らしい経験をいたしました。
振り返ってみると、長期的な展望があって今の私があるというより、その時々での偶然の出会いが今の自分につながってきたように思います。(行きあたりばったり、とも言いますが!)中学で、発音を重視する先生に教わることができたり、大学で英語音声学が必修だったり、トロント大学に行くことができたり。そしてその時にお会いした方々との出会いがあります。カナダからの帰国を決意したのも、ある日本の音韻論の学会に参加したときに、学会に参加されていた先生方がとてもフレンドリーで、こんな会があるなら参加したい、と思ったことが大きな理由でした。
今回の着任にあたっても、周りの職員の方々や先生方、そして学生さん達が親切で、皆様に助けられながら、歩み出したところです。
言語について、特に音韻(人間の音声の文法)について、自分の中で昔に比べてある程度の理解が進んできたような気も致しますが、同時に問いもどんどん増える一方です。そういったことも議論できる刺激的なキャンパスで、自分が少しでも何かの役に立つことができたら、という思いでいます。
(言語情報科学/英語)
無断での転載、転用、複写を禁じます。

