教養学部報
第661号 ![]()
<時に沿って> ミュンヘンから駒場に戻って
川野雅敬
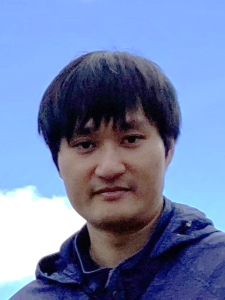 今年の十一月一日付で総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系に助教として着任しました川野雅敬と申します。私の専門は物性理論で、主に固体中電子が集団として示す性質を解析計算やコンピュータシミュレーションを用いて研究します。学位はここ駒場で取得しまして、その後二年半の間ドイツのミュンヘンに滞在し、また古巣に戻ってまいりました。「時に沿って」に何か書けるほど研究を始めてから年月が立っていませんので、ここでは直近のミュンヘン滞在で残った印象でも書いてみようかと思います。
今年の十一月一日付で総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系に助教として着任しました川野雅敬と申します。私の専門は物性理論で、主に固体中電子が集団として示す性質を解析計算やコンピュータシミュレーションを用いて研究します。学位はここ駒場で取得しまして、その後二年半の間ドイツのミュンヘンに滞在し、また古巣に戻ってまいりました。「時に沿って」に何か書けるほど研究を始めてから年月が立っていませんので、ここでは直近のミュンヘン滞在で残った印象でも書いてみようかと思います。
ドイツと聞くと「効率的」「生産性が高い」といったキーワードを聞いたことがあるのではないでしょうか? これはその通りだなと肌で実感しました。まず労働時間が短いです。平日夜遅くまで残って研究する人は(私含むアジアからの留学生を除いて)ほとんどいませんし、土日は誰もオフィスには来ません。週明けの月曜日、オフィスに向かうと必ず同僚が「週末は何してた?」と聞いてきまして、「仕事してたよ」と答えると相手がなんとも言えない微妙な顔をしてきたのを覚えています。加えて夏やクリスマスの時期には皆二、三週間ほど休暇をとって音信不通となり、基本的に仕事はしないようです。しかし、彼らはたくさん研究成果を出します。とても効率的です。いつも遊んでいる(ように見える)同僚が非常に面白い研究成果を次々と出していくのを見て、「こいつは一体いつ仕事をしてるんだ?」と思ったものです。どうやら役割分担が明確にできていて、自分の担当部分に集中して取り組むことで生産性の高さを維持しているようです。
一方で行き過ぎた効率化がもたらす弊害も経験しました。特に印象に残っているのは高速鉄道の遅延問題です。運が悪いだけかもしれませんが、私が乗った高速鉄道は一度たりとも時間通りに目的地に着いたことはありませんでした。一、二時間の遅延はまだいいほうで、そもそも電車が出発駅に来ない、または目的地に着かず途中駅(たいていは周りに何もない無人駅)で降ろされる、なども珍しくありませんでした。これは効率化に伴うコスト削減で安易に人員や路線を削減したことで、十分な余裕が確保されていないことが大きな原因の一つと聞きました。
最近では研究の現場でも、効率化を求めた結果、成果が多く期待されるテーマに人や資源が集中しすぎることを問題視する意見があります。しかし、ここ駒場はいい意味で余裕があり、自由な発想に基づいた研究ができる環境が整っているように感じます。再びそのような場所に身を置ける幸運に恵まれたことに感謝しつつ、今後も研究に邁進していきたいと思います。これからどうぞよろしくお願い致します。
(相関基礎科学/物理)
無断での転載、転用、複写を禁じます。

