教養学部報
第662号 ![]()
もっと高く天を翔けるために
教養学部長 寺田寅彦
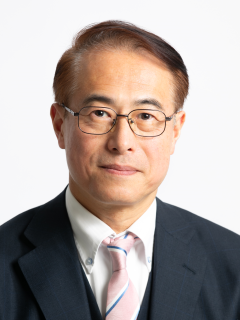 新入生の皆さん、東京大学ご入学おめでとうございます。大きな試練を乗り越えて新しいスタート地点に立っておられる皆さんに、心よりお祝い申し上げます。
もっともこれですべての試練から解放されたわけではありません。大学では定期試験がありますし、プライベートでも小さなことから大きなことまで困難はつきものです。行けども行けども砂原のようですが、そうとばかりは言えません。一九八二年二月号『教養学部報』の「飛ぶ鳩の意味」という文章の中で、モーリス・パンゲは哲学者イマヌエル・カントを引用しつつ次のようなことを述べています。「高等学校最上級の生徒だった頃、ある先生がカントの言葉を好んで引用していたのを覚えています。「飛ぶ鳩は、もし空気の抵抗がなければもっと楽に飛べるように思えるが、しかし真空の中では飛び立つことすらできない。飛べるのは翼を支える空気のおかげである。」ことばについても同じことが言えるのでないでしょうか。異国文化を研究しようとするとき、われわれには、ことばの抵抗が越えがたい障壁のように思えます。しかしじつは、この障壁こそが唯一許されている通り道なのです。」
本学で教鞭を執ったパンゲのこの文章は「外国語と「コミュニケーション・ギャップ」」というパネルディスカッションをもとにしたもので、外国語を学ぶ際にぶつかる壁こそが、その言語の持つ文化と精神を理解させてくれると説いています。羽ばたくときに邪魔に感じられる空気の抵抗こそが、自分を高みにあげてくれるものなのです。
新入生の皆さん、東京大学ご入学おめでとうございます。大きな試練を乗り越えて新しいスタート地点に立っておられる皆さんに、心よりお祝い申し上げます。
もっともこれですべての試練から解放されたわけではありません。大学では定期試験がありますし、プライベートでも小さなことから大きなことまで困難はつきものです。行けども行けども砂原のようですが、そうとばかりは言えません。一九八二年二月号『教養学部報』の「飛ぶ鳩の意味」という文章の中で、モーリス・パンゲは哲学者イマヌエル・カントを引用しつつ次のようなことを述べています。「高等学校最上級の生徒だった頃、ある先生がカントの言葉を好んで引用していたのを覚えています。「飛ぶ鳩は、もし空気の抵抗がなければもっと楽に飛べるように思えるが、しかし真空の中では飛び立つことすらできない。飛べるのは翼を支える空気のおかげである。」ことばについても同じことが言えるのでないでしょうか。異国文化を研究しようとするとき、われわれには、ことばの抵抗が越えがたい障壁のように思えます。しかしじつは、この障壁こそが唯一許されている通り道なのです。」
本学で教鞭を執ったパンゲのこの文章は「外国語と「コミュニケーション・ギャップ」」というパネルディスカッションをもとにしたもので、外国語を学ぶ際にぶつかる壁こそが、その言語の持つ文化と精神を理解させてくれると説いています。羽ばたくときに邪魔に感じられる空気の抵抗こそが、自分を高みにあげてくれるものなのです。
『純粋理性批判』序言に出てくるこのカントの飛ぶ鳩のたとえは、哲学者はもちろんのこと、さまざまな人が引用しています。よく知られているところでは太宰治の「欝屈禍」があります。この短文は『東京大学新聞』の前身である『帝國大學新聞』の七九八号(一九四〇年二月十二日付)に載ったものですが、障壁こそが文学を昇華させると説くフランス文学者のアンドレ・ジッドの芸術論を引き、カントの鳩に触れています。「「藝術は常に一の拘束の結果であります。藝術が自由であれば、それだけ高く昇騰すすると信ずることは、凧のあがるを阻むのは、その糸だと信ずることであります。カントの鳩は、自分の翼を束縛する此の空氣が無かつたならば、もつとよく飛べるだらうと思ふのですが、これは、自分が飛ぶためには、翼の重さを托し得る此の空氣の抵抗が必要だといふことを識らぬのです。同様にして、藝術が上昇せんが爲には、矢張り或る抵抗のお蔭に賴ることが出來なければなりません。[中略]藝術は拘束より生れ、闘爭に生き、自由に死ぬのであります。」なかなか自信ありげに、單純に斷言している。信じなければなるまい。」ただ、拘束や障壁は文学の敵ではなく芸術を生むものだというジッドの言葉を、太宰治は額面通りには受け取れません。「ぶん毆られて喜んでゐたのぢや、制作も何も消えてなくなる。」「不平は大いに言ふがいい。敵には容赦をしてはならぬ。」と強気に出るのですが、さて、その敵はと自問してみれば、「心中の敵、最も恐るべし」なのであって、自分自身こそは自らの芸術の障壁であり拘束であるとまとめあげたのは、昭和の大作家の面目躍如でしょう。
ところで、太宰治が引いたジッドの文章は、そもそもカントの鳩の話だったのでしょうか。太宰は河上徹太郎が訳したジッドの『芸術論』を読んでいるのですが、これは『新プレテクスト』(原題はNouveaux prétextes)の「演劇の進化」(« De l'évolution du théâtre »)というジッドの講演で、題からもすぐに察せられるように、実は同時代の演劇を古典作品なども参照しながら論じているものです。カントの鳩は講演のごく一部に過ぎず、ゲーテ、ユゴー、キェルケゴールと演劇と哲学の引用がちりばめられた演劇論なのです。また、太宰は「「私は、私の仇敵を、ひしと抱擁いたします。息の根を止めて殺してやらう下心。」これは、有名の詩句なんださうだが、誰の詩句やら、淺學の私には、わからぬ。」と書くのですが、ジッドの文章の続きを読めばこれが十七世紀古典劇作家のラシーヌの引用だと、そして察しが良ければそれは『ブリタニキュス』だとそれとなく分かる仕掛けになっているので、東京帝国大学の仏文学科にいたことのある太宰の手になるカントの鳩も文字面だけで受け取ると手痛いしっぺ返しにあいそうです。わたくしたちは壁が自分を高めるからといって、やみくもに受け入れるのではなく、距離を取り、それが何かを見極める努力をすることも大切なのです。
とまれ、冒頭に引いたパンゲもこのように書いています。「例の鳩の幻想は、今日、伝書鳩、つまり旅する鳩とでも呼べそうな形で、広く行き渡っています。時としてわれわれは、異文化における生活の実体を、見るだけで、つまり、ことばという長い回り道をせず、じかに捉えられるという気持ちを抱きます。」空気の抵抗の、試練の、束縛のおかげでこそ、皆さんが天翔ることができますように。そして、それが長く考え、遠く歩むからこそ得られる考察のうえに成り立つものでありますように。そして、その考察を可能にしてくれる教養学部での学びの日々が健やかで喜びに満ちたものとなるように祈念します。
(総合文化研究科長/教養学部長)
無断での転載、転用、複写を禁じます。

