教養学部報
第662号 ![]()
<本の棚> 橋本摂子 著『アウシュヴィッツ以後、正義とは誤謬である アーレント判断論の社会学的省察』
小山 裕
不安に抗して
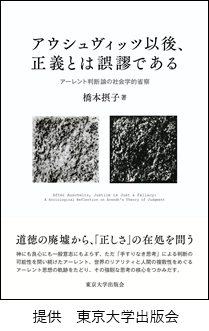 戦争や内戦に伴う人間の自由と生命の大規模かつ根底的な破壊の経験は、しばしば政治に関する原理的で独創的な思索を生み出す契機の一つとなってきた。マキアヴェッリやホッブズ、あるいは丸山眞男だけではない。本書が対象とするハンナ・アーレントもホロコーストという比類なき罪に対峙しながら自身の政治思想を彫琢していった限りにおいて、こうした政治思想史上の古典に連なる。アーレントの政治の概念は、ポリスを範例とする正統なものであり、その思索は、政治を生み出し支えるメカニズム、政治という営みの脆弱さ、そして、それを崩壊させる原因に向けられている。こうしたアーレントの試みをジンメルやルーマンらの社会学理論をも参照しながら描き出したのが本書である。
本書の主張は、アーレントがカントから継承した判断という概念には、他者への終わりなき問いかけと応答というコミュニケーション過程が含まれており、それは人間の複数性によって形作られる公的空間と構成的な関係にあるというものである。この意味での判断、そして政治という営みは、問いかけ応答する他者がいなければなされえないという意味で、人間の複数性を前提とするが、同時に、他者に問いかけ応答するというコミュニケーションは、複数性に彩られた公的空間という自らの条件を遂行的に再生産する。他者の立場からも考えるという意味での思考が可能になるのも、定義上、この循環の中においてのみである。
こうした本書の主張は、暴力や憎悪表現など人間の複数性、つまり自らと同等の尊厳を有する他者の存在を抑圧する行為や言論だけでなく、それを前提としないコミュニケーションさえも、公的世界を支えることができないばかりか、その破壊をもたらすことを示唆する。権力や権威への盲目的な服従、貨幣と商品の言語を介さない交換、専門家や著名人の言説の無批判な追従など、他者を手段としかみなさないコミュニケーションは日常に溢れている。そうした機能の上で専門分化したコミュニケーションは、しばしば合意形成のために他者を説得する手間を大幅に省略し、それぞれに備える機能的な論理に漠然と従っていれば、他者を対話の相手として明確に意識せずに生活することを可能にしている。
戦争や内戦に伴う人間の自由と生命の大規模かつ根底的な破壊の経験は、しばしば政治に関する原理的で独創的な思索を生み出す契機の一つとなってきた。マキアヴェッリやホッブズ、あるいは丸山眞男だけではない。本書が対象とするハンナ・アーレントもホロコーストという比類なき罪に対峙しながら自身の政治思想を彫琢していった限りにおいて、こうした政治思想史上の古典に連なる。アーレントの政治の概念は、ポリスを範例とする正統なものであり、その思索は、政治を生み出し支えるメカニズム、政治という営みの脆弱さ、そして、それを崩壊させる原因に向けられている。こうしたアーレントの試みをジンメルやルーマンらの社会学理論をも参照しながら描き出したのが本書である。
本書の主張は、アーレントがカントから継承した判断という概念には、他者への終わりなき問いかけと応答というコミュニケーション過程が含まれており、それは人間の複数性によって形作られる公的空間と構成的な関係にあるというものである。この意味での判断、そして政治という営みは、問いかけ応答する他者がいなければなされえないという意味で、人間の複数性を前提とするが、同時に、他者に問いかけ応答するというコミュニケーションは、複数性に彩られた公的空間という自らの条件を遂行的に再生産する。他者の立場からも考えるという意味での思考が可能になるのも、定義上、この循環の中においてのみである。
こうした本書の主張は、暴力や憎悪表現など人間の複数性、つまり自らと同等の尊厳を有する他者の存在を抑圧する行為や言論だけでなく、それを前提としないコミュニケーションさえも、公的世界を支えることができないばかりか、その破壊をもたらすことを示唆する。権力や権威への盲目的な服従、貨幣と商品の言語を介さない交換、専門家や著名人の言説の無批判な追従など、他者を手段としかみなさないコミュニケーションは日常に溢れている。そうした機能の上で専門分化したコミュニケーションは、しばしば合意形成のために他者を説得する手間を大幅に省略し、それぞれに備える機能的な論理に漠然と従っていれば、他者を対話の相手として明確に意識せずに生活することを可能にしている。
それでも人は言うかもしれない。私がそうするのは私なりに考えた結果である。いちいち他者を考慮していては非効率だし、そのぶん自分の自由な時間が失われてしまう。何より皆が納得して従っているルールの中で出世のために創意工夫し、その成果が皆に認められ、実際に昇進していくことの何が問題なのか、これは私の権利ではないか、と。こうした問いかけには、本書が指摘する複数性という事実ないし公共空間の脆弱さが端的に表現されている。複数性は偶発性を伴うがゆえに、自分の意見が拒絶されることへの不安を惹起し、同一の価値や文化といった基盤への希求を生み出す。公共空間が万人に開かれているのは、そこが誰のものでもないからであるが、だからこそ自分を含めた何者かがそれをしっかりと握りしめ、空席を埋め、安定させたいという衝動を駆り立てる。仰ぎ見るエリートたちによって自らが従うべき道徳が承認される様子を目の当たりにしたとき、アイヒマンの不安は払拭された。複数性が同一性へと、誰のものでもなかったはずの公共空間が皆のものへと静かに変容する中で、あるいは、個々人には還元しえない普遍的で公共的なものが社会による承認へとずれ込んでいくことで、「何ものにも代えがたい価値と意味」があり、「人間自らが絶対に操作してはならない不可侵の領域」(本書一七六頁)に属する複数性は侵食されていくのだろう。
複数性という事実を尊重し、その概念を継承していくという本書が読者に突きつける課題は、こうした不安や言葉の恣意的な解釈による正当化に抗して、厳密で緻密な議論を積み重ねていくことだと評者は受け止めた。基礎概念に対する大胆な読み替えや語の表記なども、評者自身の理解を再検証する契機となった。ここでは言及できなかったが、福島原発事故後の状況を克明に描いた終章は圧巻であり、必読だ。本書によって哲学と社会学の対話を前進させた著者に心から敬意を表したい。
(国際社会科学/社会・社会思想史)
無断での転載、転用、複写を禁じます。

