教養学部報
第663号 ![]()
<本の棚> 鶴見太郎 著『ユダヤ人の歴史 古代の興亡から離散、ホロコースト、シオニズムまで』中公新書
伊達聖伸
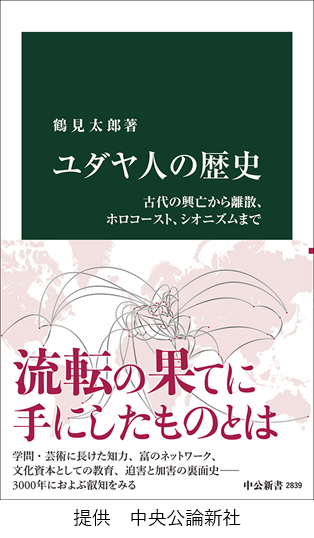 フランスの中等教育で用いられている歴史教科書で、宗教がどのように扱われているかを調べたことがある。ユダヤ教については、キリスト教の誕生と合わせて学んだあとは、中世ヨーロッパ社会におけるユダヤ共同体について触れられることもあるが、一気にドレフュス事件まで話が飛び、ホロコーストに筆が割かれるという具合だった。約70万人(全人口の約1%程度)のユダヤ人がいると言われるフランスでも、古代から現代までの歴史の歩みを学校の教科書で知るには無理がある。日本ではなおのこと、高校の世界史レベルではユダヤ人の歴史を通時的に思い描くことさえ難しい。それが、高校の教科書と並べて読める日本語でまとめあげられているのが本書である。
フランスの中等教育で用いられている歴史教科書で、宗教がどのように扱われているかを調べたことがある。ユダヤ教については、キリスト教の誕生と合わせて学んだあとは、中世ヨーロッパ社会におけるユダヤ共同体について触れられることもあるが、一気にドレフュス事件まで話が飛び、ホロコーストに筆が割かれるという具合だった。約70万人(全人口の約1%程度)のユダヤ人がいると言われるフランスでも、古代から現代までの歴史の歩みを学校の教科書で知るには無理がある。日本ではなおのこと、高校の世界史レベルではユダヤ人の歴史を通時的に思い描くことさえ難しい。それが、高校の教科書と並べて読める日本語でまとめあげられているのが本書である。
著者の専門は近現代のロシア東欧とパレスティナ/イスラエル地域だから、その時代と地域のユダヤに関してはすでに第一人者だが、これだけの範囲を叙述するのは試論的な挑戦の要素も大きかったものと推察する。専門化が進んだ現代の学術では、通史の記述は自明ではない。批判意識も研ぎ澄まされているから、たとえば近現代の概念でそれ以前のものを論じてよいのかという問題にもぶつかる。ユダヤ人の歴史と言っても、同じ集団が同一のアイデンティティを三〇〇〇年も保ち続けてきたと考えるわけにはいかない。それでもこれだけの時間幅を射程に収める本書に説得力と安定感を与えているのは、「組み合わせ」で考えるという切り口である。
ユダヤ人の輪郭は、置かれた状況と自己理解で決まってくる。外から眺める視点も内側から理解する姿勢も重要で、構造に置かれた主体がどう振る舞ったかという点に本書は焦点を合わせている。現代まで伝わるハヌカの祭りも、ユダヤのヘレニズム化という構造に抗したユダヤ人の主体性に着目するとわかりやすい。ユダヤ王国滅亡後ディアスポラになったユダヤ人は、律法を守りながら居住国の権力や住民と折り合いをつけてきた。その生き延びる知恵は、対外的にはムスリムとして振る舞ったマイモニデスにも見られる。ホスト社会とユダヤ人の共生の様子を、著者は魚のクマノミがイソギンチャクに外敵から守ってもらいつつ新鮮な海水を流し込んでいる生態に擬えている。こうした喩えは理系の読者にもイメージしやすいと思われ、卓抜な比喩が散見されるのも本書の魅力である。
ただし、共生のバランスは何かの拍子で崩れてしまいかねないものでもある。ホスト社会の権力者がユダヤ共同体に商取引の特権を与えたことは、ユダヤ人がホスト社会の庶民から得た収益を権力が吸い上げることを意味していた。搾取された庶民の不満や憎悪の矛先は、権力者よりも余所者であるユダヤ人へと向かう構図になっている。こうした三者関係の構造が、共存から排除へと暗転した典型例がポーランドである。多くの小規模貴族がいたこの地域で、ユダヤ人は土地の管理や農民からの徴税を任されて豊かな地位を築いていた。だが、近代になって貴族が没落するとユダヤ人も貧困化し、ポーランド分割の困難な状況で生まれたナショナリズムは反ユダヤ主義的な特徴を備えていた。
ロシア東欧のポグロムが世界史の教科書で言及されることは少ないと指摘する著者が、ポグロムとホロコーストを二つセットで同一の節で扱っているのも本書の特徴のひとつだろう。そして第四章を近代に、第五章を現代に割り振りつつ、ホロコーストのあとを現代の出発点とするのではなく、いったん第一次世界大戦の時期まで遡って議論を仕切り直している。ここに著者の問題意識が現われていると見るべきだろう。もともとユダヤの選民思想は、自分たちが他民族より優れているという意味ではなかった。ユダヤ教では、論争は推奨されてきたが、解釈の独占や暴力の行使は基本的になかった。ディアスポラを生き延びてきたユダヤ人は、長いあいだ武力で国家権力に対抗することはほとんどなかった。要するに、小さな平和な民だった。ところが、ポグロムやホロコーストの経験を通して自衛の意識が生まれた。イスラエルを建国し、中東の軍事大国になったあとも、被害の意識から抜け出せず、自衛の論理で加害を正当化してしまう。
ガザの惨劇を見ても、異常な組み合わせが前景化している現代だが、他の組み合わせもあると著者は示唆しているのではないだろうか。それは現代においても見られるが、歴史を遡行するとさらに見えやすくなる。そういう通史として本書を受け取ることもできる。
(地域文化研究/フランス語・イタリア語)
無断での転載、転用、複写を禁じます。

