教養学部報
第665号 ![]()
<本の棚> 細川瑠璃 著『フロレンスキイ論』
浜田華練
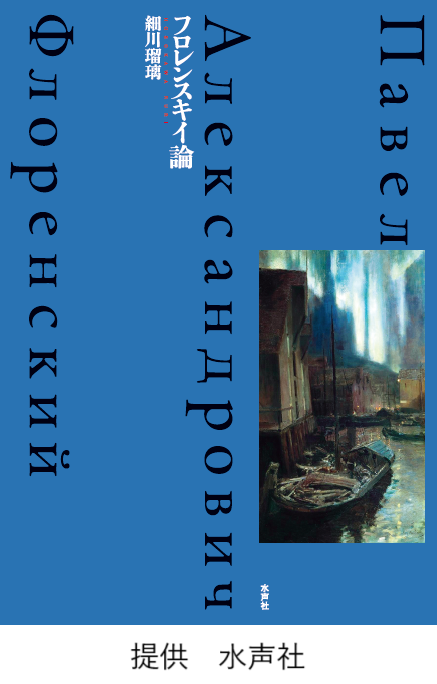 天才と呼ばれるような人物について、後世の人々がその人の「偉業」とみなす成果と、本人が才能と情熱を注いだ対象が一致しないことは珍しくない。たとえば近代科学の祖とされるニュートンが、錬金術や神学的探究に没頭したことはよく知られている。本書が取り上げるロシアの思想家、パーヴェル・アレクサンドロヴィチ・フロレンスキイ(一八八二~一九三七)も、自己評価と後世の評価のギャップが著しい人物である。
天才と呼ばれるような人物について、後世の人々がその人の「偉業」とみなす成果と、本人が才能と情熱を注いだ対象が一致しないことは珍しくない。たとえば近代科学の祖とされるニュートンが、錬金術や神学的探究に没頭したことはよく知られている。本書が取り上げるロシアの思想家、パーヴェル・アレクサンドロヴィチ・フロレンスキイ(一八八二~一九三七)も、自己評価と後世の評価のギャップが著しい人物である。
本書の帯にもある「ロシアのダ・ヴィンチ」という(本書を読めばわかるが、本人にとっては甚だ不本意であろう)キャッチコピーをつけられるほど、数学・美学・哲学など様々な学問分野に通暁し、正教会司祭でありながら革命後は技術顧問としてボリシェヴィキ政権に重用された異色の経歴をもち、強制収容所送りののち銃殺刑に処されるという悲劇的な最期を迎えた。彼の伝記である本書の第一部を読んだだけでも、その多才さと独特の感性、劇的な人生に魅了される。
ゆえに、どの部分を切り取っても面白い人物であることは間違いないのだが、その思想の全体を見通すことが困難な人物でもある。そんなフロレンスキイの思想の全体像を描き出すという難題に挑んだのが本書の第二部である。ここではその内容を詳らかにするよりは、そこで明らかにされたフロレンスキイの思想の、西洋思想史(あえて「ロシア思想史」ではなく)における意義について述べたい。というのも、著者はフロレンスキイの「功績」を殊更強調せず、彼の言葉を丹念に辿り、解きほぐすことに注力しており、そのこと自体は著者の知的誠実さのあらわれであるが、フロレンスキイがどの点において創造的かつ画期的であったのか、思想史や哲学を専門としない人々には伝わりづらいかもしれないためである。
フロレンスキイは、本書でもたびたび述べられている通り、生を肯定し、世界を善とする思想家である。哲学的姿勢としてそうであるだけでなく、収容所の過酷な環境においてさえ、生のきらめき、自然の美を見出すほどに、彼の生き方そのものであった。存在するものは善であるというテーゼ自体は、プラトン以来、(それを前提とするにしろ覆すにしろ)西洋思想の本流であった。そして、そのテーゼを成立せしめるのが、観念史の大家ラヴジョイが「存在の大いなる連鎖」と呼んだ体系である。この体系においては、至高善/絶対者が自身の善=存在を拡張させることによって、万物が善=存在を分有しているという前提のもと、善=存在の受け渡しによって至高善から下位の存在が連綿とつながる「存在論的連続性」が世界の根幹をなす。
フロレンスキイは、「連続性」において世界をとらえることを西洋近代思想の誤謬として批判し、数学の不連続関数や集合論から着想を得た「不連続性」こそが世界を正確に記述しうると考えた。だが、上述のラヴジョイが示すとおり、存在論的連続性は、フロレンスキイが理想化する中世思想にも、ひいてはキリスト教の教義にも通底する原理である。私自身が専門とする非カルケドン派神学が、カルケドン信条の二本性説を退けたのは、よく言われるように本性が一つか二つかという皮相的な理由ではなく、教理的表現に神的本性と人間本性の区別を導入することを、神と人間との存在論的連続という原則からの逸脱とみなしたためである。
フロレンスキイも、神と人間、ひいてはあらゆる存在同士の存在論的つながりを否定するどころか、むしろ絶対的真理としている。しかし彼は、二千年以上にわたり再生産されてきた「連続性」の体系に拠らず、むしろ「不連続」であるがゆえに個々の存在は互いにつながり、交流しうると主張する。本書のキーワードである〈形〉によって、「個」は「個」として存立し、他者と区別される。そこで連続性は断ち切られるのだが、しかしそれはつながりの喪失でなく、むしろ自他の稜線たる〈形〉が自己だけでなく他者の存在をも明らかにし、自他の交流の舞台となる。
異なる存在同士が、連続ではなく不連続であるがゆえにつながりうると主張するフロレンスキイは、存在論的連続性を至上命題とする人々を研究してきた私のような人間からすると、とんでもなくアクロバティックなことをやってのけているのである。もちろん、他の人から見れば、それは大したことではなく、別の点に彼の思想的インパクトが見出されるかもしれないし、むしろそうであってほしいと思う。それも含めて、ぜひ幅広い専門の方に手に取ってほしい一冊である。
(地域文化研究/ロシア語)
無断での転載、転用、複写を禁じます。

