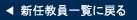新任教員紹介
越懸澤 麻衣(コシカケザワ マイ)
| 所属 | 専攻超域文化科学専 |
|---|---|
| 学科教養学科 | |
| 部会ドイツ語 | |
| 職名 | 准教授 |
| 発令年月日 | 2025年4月 1日 |
| 略歴 | ■最終学歴 東京藝術大学大学院音楽研究科 |
|---|---|
| ■学位 博士(音楽学) |
|
| ■前任職 宮城学院女子大学学芸学部音楽科 特任准教授 |
| 担当科目 | ■前期課程 ドイツ語一列①、ドイツ語中級(演習) |
|---|---|
| ■後期課程 比較文学比較文化論演習II(2)、比較文化論III(2) |
|
| ■大学院 ジャンル交渉論I |
| 研究活動 | ■研究分野 音楽学 |
|---|---|
| ■研究業績 01.「ベートーヴェン時代のポロネーズの諸相」『洗足論叢』第53巻、2025年、17~32頁。 02.「ベートーヴェンの『ハンマークラヴィーア』ソナタOp. 106のイギリス原版をめぐる状況:出版社との関係に着目して」『洗足論叢』第52巻、2024年、13~27頁。 03.『大正時代の音楽文化とセノオ楽譜』東京:小鳥遊書房、2023年。 04.“Beethoven’s Moonlight Sonata and the Japanese Reception of Western Music” Beethoven the European: Transcultural Contexts of Performance, Interpretation and Reception, Edited by William Kinderman and Malcolm Miller, Turnhout: Brepols Publishers, 2023. 05.“On the Fugues in Anton Reicha’s Quatuor Scientifique: Between Tradition and Innovation” String Quartets in Beethoven’s Europe. Edited by Nancy November, Boston: Academic Studies Press, 2022, pp. 108-129. 06.「ミッシャ・エルマンの最初の来日公演をめぐって」『洗足論叢』第49巻、2021年、1~12頁。 07.「ベートーヴェンの作品タイトルをめぐる試論」『音楽を通して世界を考える――東京藝術大学音楽学部楽理科土田英三郎ゼミ有志論集』 土田英三郎ゼミ有志論文集編集委員会編、東京藝術大学出版会、2020年、128~141頁。 08.“‘Hande’s allegro’ in Beethoven’s Diabelli Variations” Arietta: Journal of the Beethoven Piano Society of Europe 9 (2020), pp. 23-27. 09.『ベートーヴェンとバロック音楽:「楽聖」は先人から何を学んだか』(オルフェ・ライブラリー) 東京:音楽之友社、2020年。 10.バルトルド・クイケン『楽譜から音楽へ――バロック音楽の演奏法』(単訳)東京:道和書院、2018年。 |
|
| ― | |
| ― | |
| ― |
| 採用理由 | 越懸澤氏は主にドイツの18世紀・19世紀の音楽史及び近代日本の音楽史という二つの領域において幅広く研究業績を積み重ねてきた。氏の研究の特徴は、一次資料調査に基づく受容研究(ベートーヴェンのバロック音楽受容、日本におけるベートーヴェン受容について等)と音楽文化における出版社の役割(後期ベートーヴェンとイギリスの出版社との関係、大正時代におけるセノオ楽譜の意義)を解明したところにある。特記すべき点は①ベートーヴェンにおけるヘンデル受容の重要性を示したこと、②ベートーヴェンが自作をイギリスで出版しようとした際に背景にあった人的ネットワークとそれに伴う状況が作品の形式に影響を及ぼしたことを解明したこと、③セノオ楽譜という出版社とその発起人妹尾幸次郎の活動を解明し、それが、楽譜出版そのものを遥かに超える幅広い文化史的な意義を持ち、山田耕筰等音楽家の創作や演奏活動の基盤となったことを示したことである。 越懸澤氏は優秀なピアノ演奏者でありながら、楽譜の写本等のような一次資料の解読や史料批判に長け、ドイツの音楽学者とともにバロック・オペラの学術的な編集作業に関わったこともある。氏の著述がすべて一般の読者に対して開かれた平明な論述によって書かれている点も高く評価される。教学経験が豊富で学会での活動も目覚ましい。 |
|---|